2025年7月5日、6日、13日と「Yokohama Re:Portside Project」(ヨコハマ リ・ポートサイド プロジェクト)のリサーチツアーが行われました。
再開発から30年を迎えたヨコハマポートサイド地区を、現代の視点からあらためて捉え直し、新たな街の姿を見出していこうとするこのプロジェクト、まずは、アーティストユニット「片岡純也+岩竹理恵」が、ポートサイドの街をフィールドワークし、リサーチをもとに作品を制作・展示するものですが、彼ら独自のリサーチに加えて、別にコンダクターを迎え、様々な視点から地区内をめぐりながら、作品の構想を深めるものです。
このフィールドワーク(ツアー)には一般の方々も参加し、作品が生み出される過程の一部を共有できるものとなっています。
基本的には、片岡+岩竹とコンダクターのやりとりとなりますが、参加者とのやりとりも生まれ、各回内容の濃い充実した時間となりました。
7月5日は、村田真さん(美術ジャーナリスト/画家)による「パブリックアートを通して見る時代背景」です。

ヨコハマポートサイド地区内のパブリックアートを巡るツアーはこれまでも何度か行われていますが、今回はパブリックアート作品そのものを紹介するということではなく、それが設置された背景や、街が出来てきた経緯、空間といったより広い視点からのお話になっていたと思います。
開発の初期に設置された、マイケル・グレイブスの壁画、エットーレ・ソットサスの作品などに込められた思い、ナディム・カラムの軽やかな作品、気がつけば、圧倒的な迫力で迫る、菱山裕子の作品、そしてギャラリーロードに設置された、岡本敦生による旧三菱重工ドッグの石材を使った車止め、マンションに囲まれた空間にある作品、金港公園などをめぐりながら、開発にあたって、どういった意図を持ってそれらのものが設置されたか、現在のありようはどうかなどについてやりとりがありました。村田さんの「いろいろ考えて行くと、パブリックアートはどんどん丸くなってしまう」というのは、壊れたり、事故などの対応による、作品の外形的な変化に対しての発言でしたが、考えさせられるところです。

7月6日は長谷川浩己さん(オンサイト計画設計事務所)による「ポートサイド公園の楽しみ方」です。

地区内の水際線は、ポートサイド公園として整備され、憩いの場となっています。
この公園は、ヨコハマポートサイド地区の「アート&デザイン」というテーマにふさわしいものとして、コンペティションにより計画が選定されたものですが、そのデザインをしたのが長谷川氏です。
コンペならではといってもよいユニークな計画で、水際の葦原の再生や、うねりのある地面のデザイン、象徴的なファニチュアなどにより構成され、隣接する建物空間と一体的になるよう、意図されています。
ツアーでは公園をめぐりながら、特徴的なデザインが生まれた経緯や、建物との関係やスケール感のこと、再生された葦原に生まれた生態系や、デッキの使われ方、整備時期やオーナーにより隣接建物との状態が異なっていることなど、様々な点でお話がありました。

この公園だけというわけではありませんが、よく見られるベンチの寝転び防止の構造などについても、なぜこういうことをするのかについてやりとりがありました。(後付けで付加されてしまったそうです)管理と空間の豊かさ等とのバランス、なかなか難しい問題です。

7月15日は、秋元康幸さん(横浜市立大学客員教授、 BankART1929 副代表)により、「ポートサイドの街はどう生まれたか」について行われました。

歴史的な経緯等も踏まえ、充分にレクチュアしたのち、これまであまり回らなかった市場との境界部、神奈川公園などを巡り、理解を深めるものとなりました。
神奈川公園は現在工事中ですが、仮囲いに描かれたキム・ガウンさんの壁画の補修が終わった直後、良い状態で鑑賞できました。
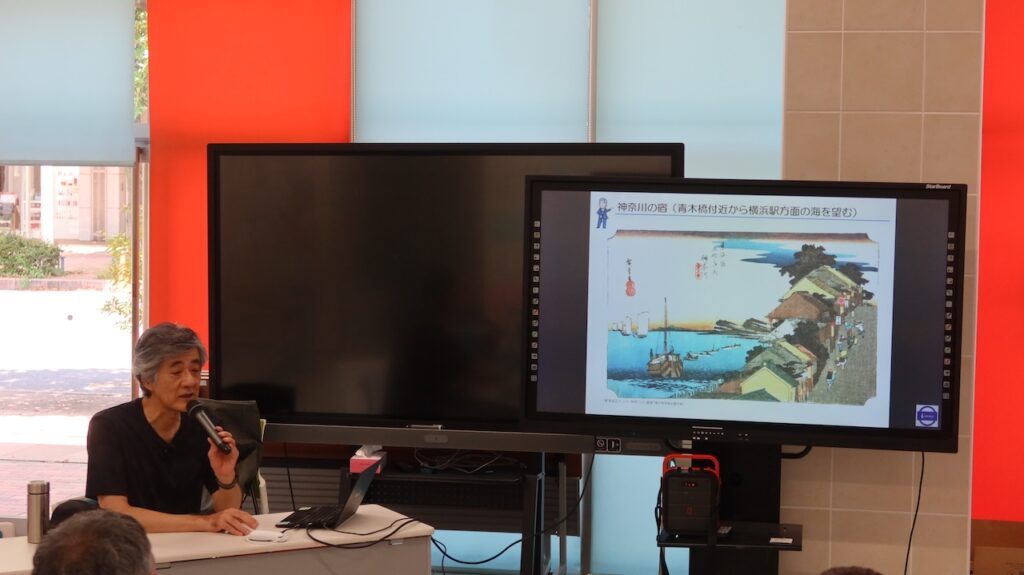
この公園は、横浜市の公園のなかでも古い時代に出来たもので、かつては公園内の道路側に「神奈川会館」というモダンな建物がありました、現在も公園内には集会所がありますが、それも、そういった建物があった名残かもしれないなど、当時の様子に思いをはせながら、ツアーを行いました。


横浜駅、市場、幹線道路の狭間にあるエリアであるポートサイドの街は、かつて海沿いを通る街道に近い、歴史的にも面白い場所です。現在のモダンな街だけではなく、周辺も含め、歴史的な視点で街を見ていくのも、大変興味深いと思います。


