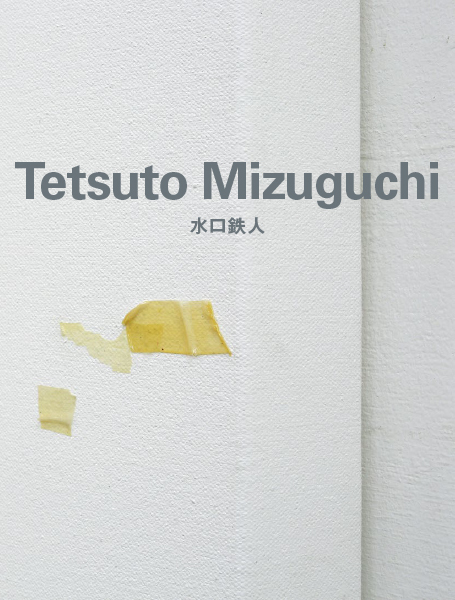恒例の福岡大川の家具メーカー広松木工家具個展が開催された。今年で5回目開催となる今回も、荒々しいコンクリート壁と真っ白な絨毯の空間に、天然木の家具たちが来館者を出迎えた。今年のテーマは「Fun with Materials!」。木材のほか、漆喰やセメント風新素材、新しい張り地など、様々な素材を取り入れ、遊び心ある新作が登場した。また猫のために作ったソファー、通称ネコ家具が大人気。家具単体ではなく空間全体での心地よさを追求し、なによりも生活を楽しむ方法を提供してくれるチームだ。
Event
陰のない花 2017年11月4日
丸山純子の花には陰がない。もっと正確にいうと丸山純子の花の写真には陰が写らない。実際に現物を見るとその環境が、自然光であろうと人工照明であろうと陰は確かに見えている。それなのに写真に写すとその姿は画面から消え、もともと存在感のない花が、ますますこの世の存在ではないかのような様相を帯びてくる。それはレジの極薄のビニール袋の透過性がなせる現象なのか?どうもそれだけではなさそうだ。
花を成立させている様々な条件を分析すると、ひとつ重要なことに気づく。丸山の花弁は、微風でも常に揺れているという事だ。そのゆらぎの振動数はカゲロウの羽の動きのように速く、眼で追いかけることはできない。静かに、揺れていないように高速で揺れ続ける。
もうひとつは、暗い空間の中で厳かに光る花弁を撮影するには、露出を絞り込んで、シャッター速度を遅くする方法しかないということだ。長時間露光の写真は、物体の動きを光の軌跡として捉え、花そのものをより実体のない世界へと導いてしまう。そしてそれを追随する花の陰は、より存在感を失い、空気のなかに溶けていってしまうのだ。こうした、「花のゆらぎ」と「長時間露光」という条件が相重なり、丸山の花から陰を消しさしてしまったのではないか。
陰のない花と名付けたのはもうひとつ理由がある。
もともとビニール袋は石油からなる加工品で、ビニール=人工物という印象を誰しもが受ける。でもよくよく考えてみると、石油の元は動物性プランクトンの死骸が堆積したものであり、生き物によって生み出されたものだ。丸山の花が、人工物であり、チープな素材でできているのにもかかわらず、何か生きているような、というより、生きているのだか死んでいるのだかわからない「なまめかしさ」を有するのはこうした背景によるのだろうと思う。そして、植物でも動物でもない、この世のものでもあの世のものではない存在感が、花から陰を奪い取っているのだと云えよう。
さらに今回の高橋の映像とのコラボレーションは、これらの分析に新たなヒントを与えてくれる。SNSなどでの感想にあるように、高橋の海を形成する青色の光が、丸山の白い花にあたると黄色やピンクや紫色の単色光を放ち始め、万華鏡のようにとても美しい。このとき花弁は陰をつくらず、プリズムのようにプロジェクターの青い光を多色に分解し、散乱させる役目をはたす。私たちの観ている光は、陰をともなわない分解された単色光だ。まさにこれが「陰のない花」の真実の姿だ。
BankART Studio NYK 閉鎖報道に関するBankART1929 からのコメント
ホームページにも掲示しましたが、
ここブログでも記載します。
いつもBankART(=特定非営利活動法人BankART1929)を応援していただきありがとうございます。新聞/雑誌による「BankART 閉鎖」というニュースがSNSを通じて飛び交い、ご心配、ご心労をかけております。遅くなりましたが、あらためて、BankART1929 から、この件に関する中間のご報告をさせていたただきます。
「BankART Studio NYK」は、確かに、来年の 3 月末日で活動を終了します。
2005 年からの一部使用時期も含めて、たくさんの皆様とともに丁寧に育んできた場所には愛着もあり、また大きな賞をいただくような重要な展覧会やイベントの開催も数多く行った場所での活動を終了することは、本当に惜しみ多いですが、現実問題として、この事実を受け入れざるをえません。
ただ BankART1929そのものが閉鎖するわけではないのです。BankART1929は来年の 4 月からもBankARTらしい活動を継続させる予定です。また、併行して、新しいプロジェクトを、横浜市が検討しているそうです。この大きな流れも見守りたいと思います。
ということで、これまでも少なくとも 3 回は引っ越ししてきているチームですので、この大嵐を楽しみながら、工夫しながら、なんとか乗り越えていければと思います。状況は刻々と変化しますが、またいくつかのことが決定次第、ご報告させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
2017年 10月
BankART1929 一同
Café Live 2017 内木里美「金魚。鮒に還る。」2017年10月7日
同シリーズ第三弾は、コンテンポラリーダンサーの内木里美の新作公演。鑑賞魚として、優雅さをもとめて品種改良を繰り返し行ってきた金魚がモチーフ。
会場には、「勉強しなさい」「もっと早く食べて」「まだ結婚しないのですか」
そんな誰かを叱る、命令する言葉たちを記した紙が柱に螺旋を描くように並べられる。内木氏がひらひらと金魚のように舞い、その後に紙を拾うという一連の動作。共演のスカンク氏は、ジャンプし続けることで、ドラムを鳴らす。舞う音、拾う音、水の音、ジャンプする音、呼吸音が響く中、太鼓の打音がそれらを打ち消す。空間・肉体・身体に向き合うアナログティックでハードな作品だった。